バウビオローゲの会
ドイツではバウビオローゲがドイツ各地で活動し、その地での住宅(新築、改修など)の相談窓口を開設しています。1年半ごとに集会をもって、互いに研鑽を積んでいます。
いままでに修了されたバウビオローゲは20数名ですが、日本でも2019年からバウビオロギー通信教育講座を修了したバウビオローゲを対象とした「バウビオローゲの集い」を実施し、より深化したテーマでの集まりを集中して持つことになりました。
バウビオローゲの集いを通じて、研究会の内的コア/エンジンを形成しつつあります。
第5回「ホールライフカーボンとバウビオロギー」
投稿日:
第5回「ホールライフカーボンとバウビオロギー」
日時:2025年 10月 24日(金)~25日(土)
会場:岐阜県立森林文化アカデミー
参加者:22名
・趣旨
近年、ZEH、ZEBが一般的になり、運用時のエネルギーやCO2排出量(オペレーショナル・カーボン)はかなり削減されてきました。そうなると、建築時、改修時、解体・廃棄時などのエンボディドカーボンの削減が重要になってきます。つまり、環境負荷を抑える素材の選定や改修しやすい建築工法など、総合的な視点が大切になってきました。
そこで、今年のテーマは建物を一生涯で考える「ホールライフカーボン(WLC)とバウビオロギー」です。
これまでもWLCを算定するツールはいろいろありましたが、入力が煩雑であったり、データが整っていなかったりと使い勝手が良いとは言えませんでした。そんな中、国交省支援のもと、ISO21930に準拠した非住宅版のWLC計算ツールJ-CAT(Japan Carbon Assessment Tool for Building Lifecycle)が昨年公開され、住宅版も準備中です。
世界的にも炭素削減のホールライフカーボンに注目が集まる中、バウビオロギー的な居住環境の視点をどのように組み合わせていくのか、バウビオローゲの方々と知見を深めたい。
・実践者の報告
・阿部哲志(岩手県庁・BIJ)
「バウビオロギー住宅とアフォーダブル住宅」
・落合伸光(家づくり工房・BIJ)
「埼玉で試行するバウビオロギーの家づくり」
・専門家セミナー
・坊垣和明(東京都市大学名誉教授・BIJ理事)
「ホールライフカーボンの行方」
・バウビオロギー討論会
「ホールライフカーボンとバウビオロギー」
田所憲一(デコス、JCA事務局長)
「脱炭素時代に選ばれる断熱材」
辻充孝(森林文化アカデミー・BIJ理事)
「ホールライフカーボンの評価事例と課題」
・森の案内人・川尻秀樹氏による森林体験プログラム




第4回「バウビオロギー に根差す改修の要点とは」
投稿日:
第4回「バウビオロギー に根差す改修の要点とは」
日時:2024 年 10 月 25 日(金)~26 日(土)
会場:公益財団法人 加藤山崎教育基金 軽井沢研修所
参加者:
・趣旨
今回のテーマは「バウビオロギー に根差す改修の要点とは」と題して、ますます重要度が増している、改修/リフォームに焦点をあてたい。主に住宅の改修を前提としている。 ローゼンハイムのバウビオロギー研究所は、平屋の雑貨屋さんに2階をのっけた改修である。以前、新しい研究所施設を考えているのだと、ヴィンフリート・シュナイダー代表から話を振られたとき、てっきり新築を考えているのだろうと思ったが、あらゆる面で見事な改修事例となった。
改修には用途や機能の変更に伴う意匠的な改修とともに、構造的な視点からの改修とともに、断熱強化を意図した改修が上げられるだろう。すべてに費用がかかるなかで、また法の縛りが少ないなかで、新築するよりは安く、、、という前提で改修が為されて、性能がアップすればそれでよいのだろうか?皆様の経験と知見を集めたい。
・実践者の報告
・石川恒夫(前橋工科大学、BIJ代表)
「バウビオロギーの改修事例」
・坊垣和明(東京都市大学名誉教、BIJ 理事)
「部分断熱改修の事例と放射暖冷房パネル」
・辻充孝(岐阜県立森林文化アカデミー/BaubiologeBIJ)
「改修による高山市、中津川市の木遊館サテライト」
・森健一郎(一級建築士事務所 感共ラボの森/BaubiologeBIJ)
「近年の事例紹介」
・専門家セミナー
・石川恒夫(前橋工科大学)
「版築を使ったプロジェクト、住宅を改修した浄泉寺の事例」
・辻充孝(岐阜県立森林文化アカデミー)
「スマートウェルネス住宅の研究成果」
・改修建築の視察・体験
・古民家を軸に改修されたカルイザワ コモングラウンズ(2023年オープン)
・軽井沢の斜面地に建つ2階建ての建物の改修
オイリュトミーの体験
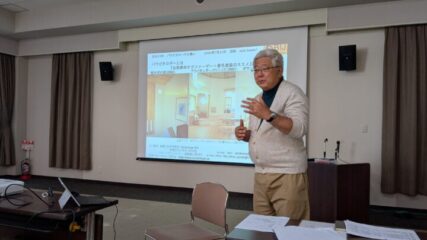

第3回「バウビオロギーの温熱環境(外皮と暖冷房設備)」
投稿日:
第3回「バウビオロギーの温熱環境(外皮と暖冷房設備)」
日時:2023年 11月 3日(金)~4日(土)
会場:岐阜県立森林文化アカデミー
参加者:11名
・趣旨
今年のテーマは「バウビオロギーの温熱環境(外皮と暖冷房設備)」
昨年、住宅性能表示制度の改定によって断熱等級5~7、省エネ等級6が追加され、日本においても温熱環境に対する意識が高まり始めている。しかし、建築実務者の中には単に断熱性能の値だけに注目している事例も多く居住環境を総合的に見据えた温熱環境への意識はまだまだ低いと言える。
そこで、本来あるべき住まい、バウビオロギーの住まいが目指す温熱環境や暖冷房設備はどのようなものかを、バウビオローゲの方々と知見を深めたい。
・実践者の報告
・辻充孝(岐阜県立森林文化アカデミー/BaubiologeBIJ)
「ドイツ視察報告:素材・エネルギーから見るエコロジー建築」
・石川恒夫(前橋工科大学/ BIJ代表)
「健康な住まいへの道」
・木津今日子(前橋工科大学)
「こころの健康―暮らしや居場所に対する満足度と主観的幸福感の相関分析」
・専門家セミナー
・石川恒夫(前橋工科大学)
「居住環境と暖房設備について」
・話題提供
・辻充孝(森林文化アカデミー)
「目指す温熱環境」
・坊垣和明(東京都市大学名誉教、BIJ 理事)
「テラスハウス、マンション改修の実例」
・バウビオロギー討論会
「バウビオロギーの温熱環境(外皮性能と暖冷房設備)」
・目指す温熱環境はどのようなものか
・外皮性能はどのように決めているか
・暖冷房設備の選択はどうしているか
・蒸し暑い日本の夏をどう乗り切るか
・換気をどのように考えるか
※会報誌No.69で報告
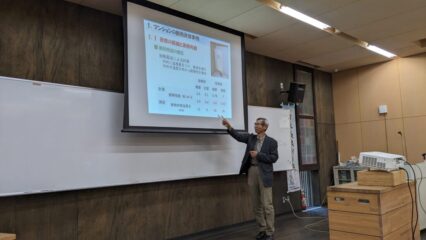

第2回「バウビオロギーに関心をもつ建築実務者のための」
投稿日:
第2回「バウビオロギーに関心をもつ建築実務者のための」
日時:2022年 11月 18日(金)~19日(土)
会場:岐阜県立森林文化アカデミー
参加者:18名
・趣旨
8月末に本会がホスト役になって、東北フォーラム(仙台)をはじめとする5団体による合同研究会が開催された(オンライン)。実務者の多くが性能値の良し悪しに一喜一憂しているなかで、「肉体と魂と精神の健康」を希求するバウビオロギーの存在価値は大きい。しかし、バウビオロギーの住まいがどのような材料を選択し、どのような性能を発揮するのか、定量的に把握することの必要性もまた大きい。
ドイツIBNとのライセンス契約に基づき、2011年に開始した≪通信教育講座バウビオロギー≫は今まで約20名のバウビオローゲ(バウビオロギー・アドバイザー)を生み出しており、2019年以来、2回目の集いを対面で実施し、お互いの経験を共有したい。そしてドイツにおける総合建築学問「バウビオロギー」の実践者とともに、日本におけるこれからのバウビオロギーの住まいの仕様を考える。
・実践者の報告
・辻充孝(岐阜県立森林文化アカデミー/BaubiologeBIJ)
「森の入り口施設 morinosの建築」
・土田直樹(レジナ株式会社、BIJ理事)
「日本の電磁波の状況と対策」
・マテーペーター(Team7、自然の住まい株式会社、BIJ理事)
「何も失わない家づくり ピュアウッド ~ヨーロッパ最先端の木質パネル~」
・専門家セミナー
・坊垣和明(東京都市大学名誉教)
「ヘルシービルディング術」
・バウビオロギー討論会
「バウビオロギーの住まいの仕様をつくる」
1.経済的な判断基準(価格、再利用、再生産可能)
2.使用方法・目的による判断基準(適材適所、耐久性)
3.視覚的・美的判断基準(色彩、テクスチャー、透明性)
4.健康的判断基準(揮発、粉塵、繊維、有毒物質)
5.エコロジカルな判断基準(LCA、廃棄時負荷、生態系)


第1回 「バウビオロギーに関心をもつ建築実務者のための」
投稿日:
第1回 「バウビオロギーに関心をもつ建築実務者のための」
日時:2019年 10月 25日(金)~26日(土)
会場:岐阜県立森林文化アカデミー
参加者:15名
・趣旨
日本における室内環境性能は主に温熱環境で議論されることが多いが、居住空間における重要さは温熱環境だけではない。電磁波、防音、空気質、光環境、色彩とさまざまである。
ドイツIBNとのライセンス契約に基づき、2011年に開始した≪通信教育講座バウビオロギー≫は今まで約20名のバウビオローゲ(バウビオロギー・アドバイザー)を生み出しており、今回はじめての集いを開催し、お互いの経験を共有したい。
・実践者の報告
・辻充孝(岐阜県立森林文化アカデミー/BaubiologeBIJ)
「カミノハウス(2014)暮らし方とDIYで省エネ+豊かさアップ」
・落合伸光(ビオクラフト/BaubiologeBIJ)
「埼玉 川越での試み」
・阿部哲志(岩手県庁/BaubiologeBIJ)
「バウビオロギーの普及に向けて
バウビオロギーを通して考える住環境と人間との全体的諸関係」
・江藤眞理子(空設計工房/BaubiologeBIJ)
「バウビオロギー+パッシブデザイン 熊本パッシブハウスでの試み」
・専門家セミナー
・石川恒夫(前橋工科大学)
「バウビオロギー25の指針
自然のメカニズムと住まいの柔らかい呼応を求めて」
・辻充孝(森林文化アカデミー)
「非定常計算でわかる断熱材の蓄熱効果と夏型結露対策」
・坊垣和明(東京都市大学名誉教授)
「ふく射冷暖房のすすめ」
・バウビオロギー討論会
通信講座第4巻「建築工法」の巻末の仕様規定をもとに、今、私たちが住まいづくりにおいて求められている諸性能や諸課題を話し合いました。
※会報誌No.60で報告


